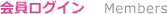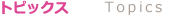別居中の復縁コメント No.8331
こんにちは。
謝罪をしたのですね。メールか手紙で迷っているとおっしゃっていたので、
まさか電話をするとは思っていませんでした。
おそらく恋愛回路がそうさせたのだと思いますが、残念です。
電話だとつい余計なことを言ってしまいがちですし、相手にもこちらの言葉を咀嚼するための時間を与えません。タイミングによっては相手の都合が悪いでしょう。
復縁はいつでも難しいもの、さらにぷうさんは何度も復縁を繰り返し(嫌な感情が蓄積)、結婚までしてその結婚さえも撤回されようとしていますので、復縁の可能性はもともと非常に低いと思います。
今後は感情のコントロールをこのサイトなどで学び、冷静に対処できるようにするとよいと思います。
選択肢は2つしかありません。
感情のままにふるまって関係を悪化させるか、もしくは復縁を優先して辛くても感情をコントロールするか、です。
感情のままにふるまって思い通りの結果を得るという都合のよい選択肢はありません。
難しいことだとは承知していますが、これができなければ博士理論を勉強しても無意味です。
さて、きつい言い方をしてしまい申し訳ありません。
ですが、このままぷうさんが感情に支配され続けるなら、私がどんなに意見をいってもぷうさんのお役に立てることはないと思います。そのためきつくても述べさせていただきました。
自分のことを責めるのではなくて、過ぎたことはしっかりと反省材料にして、これからのことを前向きに考えましょうね。
今、ぷうさんができることは「何もしない」ことだけです。
他にはなにもありません。
これは彼に対してであって、自分磨きとか、気分転換に運動するなどはぜひぜひやってください。
自分のよかったことや反省点をノートに書くなど、分析もよいと思いますが、今はぷうさんの恋愛回路を強化してしまいそうなのであまりおすすめできません。
とにかく、ぷうさんの恋愛回路は超強力なようなので、他のことに気を向けるよう努力してください。
それから、謝罪の手紙/メールはもともと相手の反応を期待してするものではありません。ですから、謝罪したからといって彼の態度や気持ちが変わるなどと期待しないでください。
また、謝罪の連絡をしたせいで離婚が早まったのではと危惧されていますが、冷静に考えてみてください。
別居中の妻と離婚しようと考えている男性が、妻から謝罪の連絡があったからといって離婚を早めようと思いますか?それとも離婚を早めたくなるようなことを言ってしまいましたか?謝罪と感謝のみでしたら、大丈夫だと思いますよ。もともと離婚する気でいたからそれを伝えたまでではないでしょうか。
今後の対応ですが、私の考える方針を書きます。が、これは離婚も含めた方法なので、ぷうさんが受け入れられるかどうかわかりません。それにいつでも復縁は可能性が非常に低いことを念頭に置いてください。
●ご主人から連絡があるまでこちらからはいっさい(一切!ですよ)連絡しない。
その間、ぷうさんはこのサイトで勉強したり、自分磨きをしたり、外の世界に強制的に目を向けてください。
●ご主人から連絡が来たら、会いましょう。おそらく離婚の手続について話し合いを持ってくると思います。その際、ぷうさんは、ご主人が離婚したいならそれに応じましょう。縋ったりしてはいけません。ご主人の負担/ストレスになるからです。ご主人の負担ができるだけ軽くなるように(もちろんご自分が無理する必要はありません)、手続を進めましょう。「今までありがとう。残念な結果になったけど、これからの貴方(ご主人)の人生を応援しているよ」という態度で接します。離婚の手続を進めながら、居心地の良さを提供します。
●ご主人の気が変わることなく本当に離婚になっても、受け入れます。もう一度、感謝を述べてもいいと思います。ぷうさんが離婚の覚悟ができていなくても、一方的な感情では結婚生活は成り立ちませんよね(経済的援助だけ受けれればいいなどの理由を除き)。そんな結婚生活は辛いだけではないでしょうか?思い通りにならないことは「受け入れる」しかありませんし、そうすると楽になります。
離婚後は、他の出会いを探しながら、完全な沈黙です。ご主人から連絡が来る時期は予想が難しいですが、連絡が来たら、「ダメ出しをしすぎた場合」の通常のプロトコール通りにします。このとき、ご主人の言葉に振り回されず行動で判断するように注意してください。
離婚になったら、ご主人は死んだと思って、他の出会いを探してください。
おそらく恋愛回路から解放されたら、どうしてあんな人にあんなに必死になっていたんだろうと思うと予想します。
気が向かなくても強制的に外の世界を見て、外の世界に接していきましょう。
以上が私の考える対応策です。ご参考まで。くれぐれもご自分でよく考えて納得のいく答えを見つけてください。
さらに長文になってしまいますが、ぷうさん自身について気になることがあるので書かせていただきます。
ぷうさんは「共依存」についてはご存知でしょうか?もし機会があれば、関連書籍を読んでみるとよいと思います。これまでご主人に構いすぎて、ぷうさんが自分の人生を生きておらず、ぷうさんがご主人のためにばかり行動していたような印象を受けました。
また、「認知の歪み」について以下に適当なHPから抜粋したものを記載します。
当てはまるものがあるでしょうか?
これらの考え方は歪んでおり、自分を苦しめるものであって、これを矯正することによってずいぶん楽になると思います。参考まで。
***以下抜粋***
1.全か無か思考(all-or-nothing thinking)
ほとんどの問題は, 白か黒かのどちらかに決めることはできず、事実はそれらの中間にあるものですが、物事を見るときに、「白か黒か」という2つに1つのの見方をしてしまうことを「全か無か思考」といいます。
<例>自分のやった仕事に少しの欠点が見つかって、「完全な失敗だ」と思う。
いつもAをとっている学生がたまたまBをとって,「もう完全にだめだ」と考える。
「白か黒か」という2つに1つの見方をせずに、いろいろな場合があるというように、広くものを見ることが大切です。
2.一般化のしすぎ(overgeneralization)
1つの良くない出来事があると,「いつも決まってこうだ」、「うまくいったためしがない」などと考えること。
<例>ある若い男性が、好きな女性に一度デートを申しこんで断られただけなのに、「いつ
もこうだ。自分は決して女性とつきあうことなんかできない」と考える。
このような考え方をすると、いやなことが繰り返し起こっているように感じてしまうので、憂うつになってしまいます。
3.心のフィルター(mental filter)
1つの良くないことにこだわってくよくよ考え、他のことはすべて(いいことも)無視してしまうこと。
ちょうど1滴のインクがコップ全体の水を黒くしてしまうように。「心のサングラス」ともいう。
<例>会社である計画を考えて、たいていの人の評価はたいへんよいのに、ある人から受
けたちいさな注意が頭からはなれず悩む。
このような思考パターンに陥ると、なにごともネガティブ(良くない方向の考え方)に見てしまうので、気分は、当然暗くなります。
4.マイナス化思考(disqualifying the positive)
単によいことを無視するだけでなく、なんでもないことやよい出来事を悪い出来事にすり替えてしまうこと。
<例 >自分は能力がないと考えている人が、仕事がうまくいっても「これはまぐれだ」と考え
仕事がうまくいかないときは、「やっぱり、自分はダメなんだ」と考える。
よかった出来事や成功したことの価値を引き下げることになり、ますます悪い「認知のゆがみ」のパターンということができます。
5.結論の飛躍(jumping to conclusion)
特に確かな理由もないのに悲観的・自分は良くないんだ・悲しいというような結論を出してしまう。
a. 心の読みすぎ(mind reading):ある人が自分に悪く反応したと早合点してしまうこと
<例>会社の上司に仕事の進み具合を伝えたが、上司はあまり関心をはらってくれない、
むしろそっけない態度のように思え、「この頃、自分は上司に嫌われている」と考え
た。
(上司は、例えば、そのことよりも急ぎの用があって、そっちの方に心がいっていただ
けかもしれない。)
b. 先読みの誤り(the fortune teller error):今の様子は確実に悪くなると決めつけること
<例>「この病気は決してなおらない」と考える。
(うつ病になるとこのような考え方になることがよくあります。)
6.誇大視と過小評価(magnification and minimization)
自分の短所や失敗を大げさに考え,逆に長所や成功したことをあまり評価しない。
「双眼鏡のトリック」とも言う。
<例> たいしたことのない小さななミスをおかして、「なんてことだ。これですべて台無しだ」
と考える。
7.感情的決めつけ(emotional reasoning)
自分の感情が現実をリアルに反映して、事実を証明する証拠であるかのように考えてしまうこと。
<例>「不安を感じている。だから失敗するに違いない。」
8.すべき思考(should thinking)
何かやろうとする時に「~すべき]「~すべきでない」と考える。
<例>「あの時、父親は怒るべきではなかった。」
物事の好き嫌いは別として、おこったことは現実として受け入れることが大切です。)
何かをやろうとするときに、常に「~すべき」「~すべきでない」と考えると、その基準に合わせようとして自分自身を追い詰めることになります。
できなかった場合は、あたかも自分が罰せられたように感じて、自分で自分が嫌いになったり、暗い気分になったりしやすいのです。「すべき思考」を他人に向けると、他人の価値基準とはたいていの場合は合いませんから、それでイライラや怒りを感じることになります。
9.レッテル貼り(labeling and mislabeling)
ミスや失敗をした時に,「自分は負けだ」、「とんまもの!」などと自分にネガティブなレッテルを貼ってしまうこと。
レッテル貼りは、「一般化のしすぎ]がはっきりとした形で現れたものです。レッテル貼りをすると、感情に巻き込まれて冷静な判断ができなくなります。
10.自己関連づけ(personalization)
何か良くないことが起こった時、自分に責任がないような場合でも自分のせいにしてしまうこと。
<例>酒を飲まないと約束したのにできない夫を前にして、「自分はダメな妻だ。夫が酒を
やめることができないのは自分の責任だ」と考える。
他人に100%の影響を及ぼすことは不可能です。
よくないことがおこった場合、それを自分の責任と考えるよりは、どうすれば問題を解決できるのかを考えるほうがより健全で大切なことなのです。
「自己関連づけ」の思考パターンを繰り返すと、罪の意識を感じることになり、その結果自己評価が低下してしまいます。
***ここまで***
以上、超長文になってしまいました。
繰り返しますが、ぷうさんが自分が幸せになるための選択・行動ができますように。
- [44歳]

 うみこ ランク圏外
うみこ ランク圏外
※「別居中の復縁」の全コメント
- ぷうさん、こんばんは。mikといいます。
辛い状況とお察しします。
投稿内容について…
うみこ -- (No.8155) 2012-05-26 10:24- >mikさん
お返事ありまとうございます。
どうしていいかわからず悩んでいたのでとてもうれし…
ぷう(投稿者) -- (No.8184) 2012-05-27 17:17
- >mikさん
お返事ありまとうございます。
どうしていいかわからず悩んでいたのでとてもうれし…
- >ぷうさん
お返事ありがとうございます。
コメントが遅くなってしまい、すみません。
少…
うみこ -- (No.8246) 2012-06-01 12:46 - お忙しい中お返事ありがとうございます。
補足致します。
まず、ご主人は、自分が悪者になり…
ぷう(投稿者) -- (No.8303) 2012-06-01 23:41- >ぷう(投稿者)さん
こんばんは。とりいそぎ、謝罪の手紙/メールの件についてお返事します。…
うみこ -- (No.8305) 2012-06-02 01:42
- >ぷう(投稿者)さん
こんばんは。とりいそぎ、謝罪の手紙/メールの件についてお返事します。…
- mikさんへ
お返事ありがとうございます。
先日謝罪&感謝の連絡をしました。
メー…
ぷう(投稿者) -- (No.8330) 2012-06-03 14:42 - ぷう(投稿者)さん
こんにちは。
謝罪をしたのですね。メールか手紙で迷っているとおっし...
うみこ -- (No.8331) 2012-06-03 21:28 - 連投してすみません。
追記させてください。
離婚を受け入れるまえに何かしたいのでしたら、…
うみこ -- (No.8352) 2012-06-04 01:55 - mikさんへ
お忙しい中たびたびアドバイスいただき本当にありがとうございます。
友人にも…
ぷう(投稿者) -- (No.8431) 2012-06-05 22:33 - >ぷうさん
こんばんは。お返事ありがとうございます。
今回のコメントはアドバイスではありませ…
うみこ -- (No.8436) 2012-06-05 23:47 - mikさん
お返事ありがとうございます。
返事が遅れてしまいすみません。
いつも親…
ぷう(投稿者) -- (No.8632) 2012-06-11 21:08